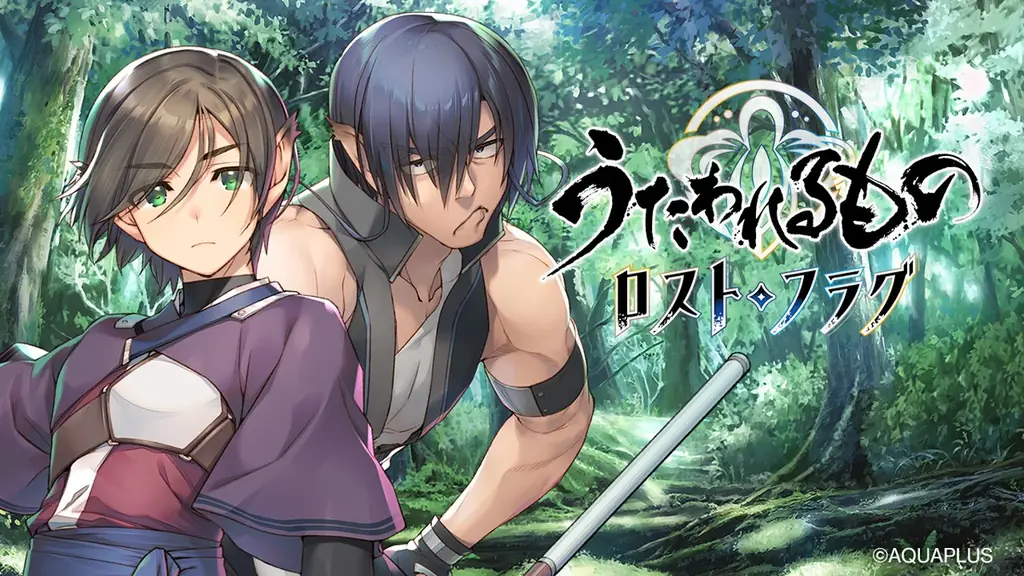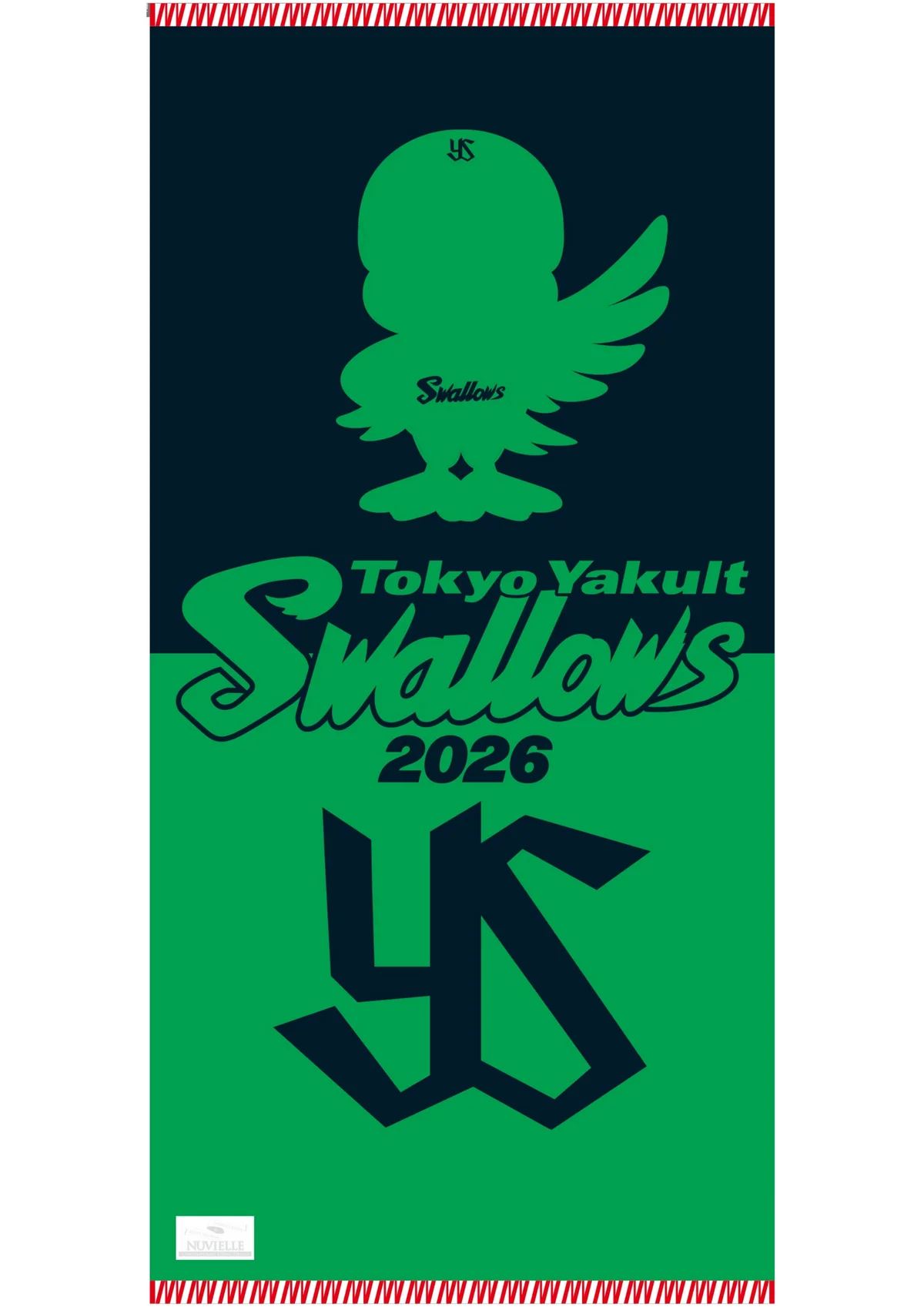第1章:2025年度(4月始まり)概要
2025年度とは、2025年4月1日から2026年3月31日までの期間を指します。日本の学校や官公庁、企業の多くは4月始まり・3月終わりの年度区切りを採用しており、新入学・新入社や人事異動などがこの時期に集中します。特に2025年度は、以下のような注目すべき要素が数多く存在します。
- 日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催:2025年4月13日~10月12日
- 世界陸上2025(東京)の開催:2025年9月13日~9月21日
- 法改正や制度変更:建築基準法改正や育児・介護休業法など、4月1日施行が多数
- 大企業や官公庁では新年度予算の執行開始、人事異動の集中
- 学校では始業式・入学式が行われ、一斉に新学年・新学期がスタート
また、2025年度は暦のうえで「平年」であり、2月は28日までとなります。連休や祝日の配置により、GW(ゴールデンウィーク)や年末年始にやや長めの休暇が発生しやすい年です。以下の章では、2025年度の年間スケジュールをより詳しく見ていきましょう。
第2章:年間カレンダー概観(祝日・連休)
2-1. 2025年度に含まれる祝日一覧
2025年度内(2025年4月1日〜2026年3月31日)に該当する祝日・振替休日は下表のとおりです。
| 日付 | 祝日名 | 備考 |
|---|---|---|
| 2025年4月29日(火) | 昭和の日 | |
| 2025年5月3日(土) | 憲法記念日 | |
| 2025年5月4日(日) | みどりの日 | |
| 2025年5月5日(月) | こどもの日 | |
| 2025年5月6日(火) | 振替休日 | 5/4(日)の振替 |
| 2025年7月21日(月) | 海の日 | 7月第3月曜 |
| 2025年8月11日(月) | 山の日 | |
| 2025年9月15日(月) | 敬老の日 | 9月第3月曜 |
| 2025年9月23日(火) | 秋分の日 | |
| 2025年10月13日(月) | スポーツの日 | 10月第2月曜 |
| 2025年11月3日(月) | 文化の日 | |
| 2025年11月23日(日) | 勤労感謝の日 | |
| 2025年11月24日(月) | 振替休日 | 11/23(日)の振替 |
| 2026年1月1日(木) | 元日 | |
| 2026年1月12日(月) | 成人の日 | 1月第2月曜 |
| 2026年2月11日(水) | 建国記念の日 | |
| 2026年2月23日(月) | 天皇誕生日 | |
| 2026年3月20日(金) | 春分の日 |
2-2. 注目の連休と休日の並び
- ゴールデンウィーク:2025年は5月3日(土)〜5月6日(火)の4連休。ただし4月29日(火)を含めた休暇を計画すれば、最大8連休に拡大可能です。
- お盆休み:お盆(8月13〜16日)は通常平日扱いですが、8月11日(月:山の日)や週末と組み合わせて長期休暇を取得できる企業が多い傾向です。
- 年末年始:2025年12月27日(土)〜2026年1月4日(日)が最大9連休になります(官公庁は12月29日〜1月3日が正式休暇)。
- シルバーウィーク:2025年は9月13日(土)〜15日(月)の3連休や9月21日(日)〜23日(火)の3連休がありますが、大型連休(5連休)は発生しません。
このように、カレンダー上の祝日配置によっては複数の連休が発生します。特にGWと年末年始は長期旅行や帰省を計画しやすいタイミングと言えるでしょう。
2-3. 六曜・月齢・二十四節気など
日本のカレンダーでは、祝日以外にも六曜(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口)や月齢(新月・満月)、さらに二十四節気や雑節などを併記する習慣があります。2025年度では以下のポイントに注意するとカレンダーをより活用できます。
- 六曜:4月1日は「赤口」、4月6日が「大安」など6日周期で繰り返されます。結婚式や葬儀の日取りに影響する場合もあります。
- 月齢:2025年9月8日の満月(中秋の名月)は皆既月食、9月22日の新月は部分日食など天文現象が重なります。
- 二十四節気:春分(3/20)や秋分(9/23)は祝日と重なり、暦と休日がリンクします。
- 雑節:土用の丑の日(7月25日、8月6日など)や彼岸(3月・9月)、入梅(6月上旬)など、季節行事の目安になります。
第3章:学校関連スケジュール
3-1. 学期区分と長期休暇
公立小中高校はほとんどが「4月始まり・3月終わり」の学年制を取っています。多くの地域で3学期制を採用しており、以下のように区分されるのが一般的です。
- 1学期:4月上旬(始業式)~7月下旬(終業式)
- 夏休み:7月下旬~8月末
- 2学期:9月1日頃~12月下旬
- 冬休み:12月下旬~1月上旬
- 3学期:1月上旬~3月下旬
- 春休み:3月下旬~4月上旬
実際には地域によって若干のずれがあります。例えば北海道は夏休みがやや短く、冬休みが長い傾向です。都市部でも猛暑対策等で夏休みの開始時期を前倒しする自治体があり、正確な日程は各教育委員会や学校の配布する行事予定表を確認してください。
3-2. 受験シーズン
年度内には、高校・大学入試などの重要日程が集中します。以下が例です。
- 高校入試(公立):
- 3月上旬~中旬に学力検査および面接を実施
- 合格発表は3月中旬
- 大学入学共通テスト:
- 1月中旬の土日(2026年度入試は2026年1月17・18日予定)
- 私立大学の個別試験は1月下旬~2月中旬頃
- 国公立大二次試験:
- 前期日程:2月下旬
- 中期・後期日程:3月上旬
合格発表は3月に集中し、合格者は4月上旬の入学式に臨みます。なお私立校(中学・高校)は2月に入試を行うケースが多く、地域や学校ごとに異なるので要チェックです。
3-3. 学校行事と式典
1年間の学校行事として、4月に入学式・始業式、7月下旬に終業式、12月下旬に終業式、1月上旬に始業式、そして3月に卒業式・修了式を迎えるのが一般的です。特に4月上旬は多くの式典が重なるため、保護者や地域コミュニティでも行事が活発です。
また文化祭・体育祭・合唱祭などの校内行事は、概ね初秋〜晩秋(9〜11月)にかけて集中することが多く、学外でもPTA行事や地区運動会と絡んで多忙な時期になります。近年は感染症対策のため大規模イベントを制限している地域もありますが、2025年度は社会状況に応じて徐々に制限緩和が進むことが予想されます。
第4章:ビジネス・行政の年度区切り
日本では多くの企業や行政機関が4月始まり・3月終わりの会計年度を採用しています。2025年度(2025年4月1日〜2026年3月31日)においても、官公庁をはじめとして企業の予算編成や決算、人事異動などが4月を基点に動きます。以下では、ビジネスや行政の観点から年度区切りにまつわる主なトピックを詳しく見ていきましょう。
4-1. 会計年度と決算の流れ
会計年度とは、収支の管理を1年間区切りで行うための基準期間です。ほとんどの公的機関は4月に始まり翌年3月末に終わる形をとっており、企業でも同じスケジュールを採用しているケースが多く見られます。具体的な流れは以下のとおりです。
- 予算策定:年度開始前の1〜3月頃に新年度予算が立案・審議され、4月1日から執行がスタートします。
- 年度初め(4月):官公庁や企業の事業計画が本格的に動き始める時期で、プロジェクトや新サービス、制度のローンチが集中することが多いです。
- 中間決算(10月〜11月頃):半期分の業績を確定し、経営指標の再確認を行います。必要に応じて予算修正や増減資の検討が行われるケースもあります。
- 年度末(3月):決算作業が本格化し、経理部門や会計事務所は繁忙期となります。税務申告や決算報告書の作成など、書類手続きにかかる負荷が高まります。
- 株主総会(6月頃):3月期決算の企業は、年度終了後の5月下旬〜6月に定時株主総会を開催し、決算承認や役員の改選など重要事項を決定します。
4-2. 人事異動・新卒採用の集中
日本の新卒採用は4月入社が圧倒的に多いため、大学生の就職活動や企業の採用スケジュールもこれに合わせて展開されます。2025年度の場合は、2026年3月卒業予定の学生が2025年の春〜夏にかけて本格的な選考を受け、内定が固まると2026年4月に入社を迎える流れとなります。加えて、民間企業・官公庁ともに4月1日付での人事異動が通例化しているため、3月末〜4月上旬にかけて職場の組織体制が大きく変わります。
- 新入社員の入社式:多くの企業が4月1日に実施し、新入社員研修やオリエンテーションが同月中に集中します。
- 異動・転勤:地域・部署替えなどの人事発令が4月1日付で行われ、特に官公庁や銀行、教職員においては大規模なシャッフルが生じます。
- 中堅層のキャリア転換:4月の組織改編に伴い、管理職への昇進、他部署への異動などキャリアパスが変化する節目となる人も少なくありません。
このような人事の集中により、4月はビジネスシーンが一気に動き出すタイミングです。新部署での目標設定や組織の編成方針が固まりやすく、年度初めならではの活気を感じられることが多いでしょう。一方で、異動者の引継ぎ不足や新人研修による業務負荷が高まる懸念もあるため、組織的なスムーズな環境整備が求められます。
4-3. 税務関連と法改正
税務・労務面での改定や法律の施行日も4月1日が多く設定されます。具体例としては、雇用保険料率の改定、最低賃金法・育児・介護休業法の改正、法人税法や地方税法の一部改正などが挙げられます。2025年度にも各種改正法案が4月1日に施行される見込みで、ビジネスへの影響は少なくありません。
- 雇用保険法改正:失業給付や育児休業給付の支給要件見直し
- 建築基準法の改正:省エネ基準適合の義務化や許認可要件の変更
- 労働基準法関連:残業規制の適用拡大や有給休暇取得義務の適用範囲拡大など
企業は新年度スタートにあわせて、これらの法改正への対応や社内規定・就業規則のアップデートを一斉に行う必要があります。特に働き方改革関連や少子高齢化社会に伴う育児・介護施策強化の流れは今後ますます進むため、経営や人事担当者は常に最新の制度動向を注視しておくことが重要です。
4-4. 行政サービスと地方自治体の動き
自治体でも4月1日付の新年度開始にあわせ、新組織の発足や条例改正、料金改定などが実施されます。市町村合併に伴う区画変更や公共施設の運営形態変更、各種届出受付のシステム更新など、住民の生活にも影響する動きが年度替わりに集中しがちです。
- 住民税の切り替え:前年の所得に応じて6月から特別徴収が始まり、自治体ごとに税率や控除額が更新されることもあります。
- 固定資産税の納税通知:4月頃に新年度分の納税通知書が発送されます。
- 子育て支援策:保育園・幼稚園の入園申込や補助制度が年度単位でリセットされ、新たな受付や選考が進められます。
このように、4月は公私ともに大きな変化が訪れる月です。次章では、季節の行事やイベント面から2025年度を捉えてみましょう。
第5章:季節の行事・イベントとトピック
日本は四季がはっきりしており、それぞれの季節に合わせた行事やイベントが充実しています。2025年度も例年どおり、春夏秋冬それぞれの魅力に応じた催しが全国各地で開催されるでしょう。さらに2025年は「大阪・関西万博」や「世界陸上2025」が予定されるなど、国際的なビッグイベントも目白押しです。
5-1. 春の行事(4〜5月)
4月は入学式や新社会人の入社式など“始まり”の季節です。各地で桜が開花し、花見シーズンが到来します。開花日は地域によって異なり、九州・四国地方では3月下旬から、東北・北海道は4月下旬〜5月上旬と時期がずれます。首都圏のソメイヨシノは3月下旬〜4月上旬が見頃になることが多く、新生活のスタートとあわせて賑わいを見せます。
- 花まつり(灌仏会):4月8日、お釈迦様の誕生日を祝う仏教行事。甘茶をかける習わしがあります。
- 藤まつりやツツジ祭り:4月下旬〜5月上旬に各地の花名所で開催され、ライトアップや屋台などが楽しめます。
- ゴールデンウィーク:4月末〜5月上旬の連休。行楽地やイベントが大変盛り上がり、高速道路や空港は混雑必至です。
5月には端午の節句(こどもの日)や母の日など家族行事が多く、屋外レジャーにも最適な時期です。自然公園や遊園地、キャンプ場などは連休を中心に多くの人出が予想されるため、事前の計画があると快適に過ごせます。
5-2. 夏の行事(6〜8月)
梅雨(6月)を抜けると、強い日差しの夏が到来します。2025年の梅雨入りは全国的に平年並みと予想され、関東甲信では6月上旬〜中旬頃、梅雨明けは7月中旬〜下旬頃が目安です。夏は多彩な祭りや花火大会、盆踊りなど日本の伝統文化が最も華やぐ季節でもあります。
- 七夕(7月7日):短冊を吊るして願いごとをする風習があり、各地で七夕飾りが人気を博します。仙台では毎年8月6日〜8日に「仙台七夕まつり」が盛大に行われます。
- 夏祭りと花火大会:代表的なものに、東京隅田川花火大会、大阪天神祭、青森ねぶた祭、秋田竿燈まつり、徳島阿波おどりなどがあります。数十万人から百万人規模の人出になることも珍しくありません。
- お盆(8月13〜16日):先祖の霊を迎え、送り火を焚くなどの伝統行事がある時期です。帰省ラッシュが起こり、高速道路や鉄道が非常に混雑します。
また、2025年夏の大きなイベントとしては、大阪・関西万博(2025年4月13日〜10月12日)が挙げられます。暑い季節に万博会場へ訪れる場合は、熱中症対策(帽子や日傘、水分補給など)が必須です。全国的に台風シーズンも7月下旬〜9月頃まで続くため、気象情報のチェックを怠らないようにしましょう。
5-3. 秋の行事(9〜11月)
台風が通り過ぎるとともに、次第に秋の気配が深まってきます。9月には敬老の日や秋分の日を含む連休があり、俗に「シルバーウィーク」と呼ばれる大型休暇が生じる年もあります。2025年はやや短めの連休が複数回ある程度ですが、紅葉狩りや行楽のタイミングにはぴったりです。
- 中秋の名月(2025年9月8日):十五夜にあたる満月で、しかも皆既月食が重なります。月見団子を供えるなど、昔ながらの風情を楽しめます。
- 秋祭り:収穫祭や神嘗祭、だんじり祭など、各地域で独自の伝統行事が盛り上がります。
- 紅葉シーズン:10月下旬〜11月にかけて全国的に色づきが進みます。京都や日光、北海道の大雪山などは例年多数の観光客で賑わいます。
2025年9月13日〜9月21日には、世界陸上2025(東京)が開催予定です。世界中のトップアスリートが集結し、大会期間中は競技会場の国立競技場を中心に大きな盛り上がりが見込まれます。興味のある方はチケット情報や周辺交通規制について随時チェックが必要です。
5-4. 冬の行事(12〜2月)
年末年始の行事は日本人にとって欠かせない伝統的なイベントが詰まっています。クリスマスやイルミネーションから始まり、大晦日の除夜の鐘、正月の初詣など、季節感あふれる行事が目白押しです。
- 年末年始(12月〜1月):多くの企業は12月末に仕事納めし、1月上旬(1月4日 or 1月5日)に仕事始めを迎えます。2025年末〜2026年始は暦の並びがよく、最大で9連休を得られる場合があります。
- 節分(2月3日頃):豆まきや恵方巻きを食べる風習が一般化し、全国で行事として定着しています。2026年の節分は2月3日(火)に当たります。
- 受験シーズン:1〜2月に大学入学共通テストや私立大入試、国公立大二次試験(2月下旬、3月上旬)が連なり、受験生にとっては最も重要な時期です。
1月1日の元日は国民の祝日となり、多くの人が神社仏閣へ初詣に出かけます。2月には各地で雪まつり(札幌・青森・秋田などの雪国)や温泉イベントが催され、ウインタースポーツを満喫できる時期でもあります。
第6章:2025年度の防災意識と自然災害への備え
日本は地震や台風、豪雨などの自然災害が多い国として知られています。年度カレンダーを活用する際、行事や休日のみならず、「災害リスク」や「防災の取り組み」も視野に入れておくことが大切です。2025年度においても、地震や台風、水害、火山噴火などのリスクは常に存在し、特に梅雨〜秋にかけては台風被害や豪雨被害が懸念されます。以下では、2025年度に注目すべき防災ポイントと対策を詳しく掘り下げます。
6-1. 地震・津波に対する備え
日本は世界有数の地震多発国であり、南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの発生リスクが指摘されています。2025年度中に発生するかどうかは不明ですが、万が一の事態に備えることは不可欠です。特に沿岸部では地震と同時に津波が発生する可能性もあるため、避難計画や避難先施設の確認が急務となります。
- ハザードマップの確認:自治体が作成する津波浸水予想図や液状化マップを入手し、自宅や学校、職場の避難場所・ルートを共有する。
- 非常食・備蓄品の準備:水や食料のほか、ラジオ、懐中電灯、モバイルバッテリー、常備薬などを一定量キープしておく。
- 防災訓練:地域や職場、学校単位で行われる防災訓練に積極的に参加し、緊急時の行動を身体で覚える。
特に年度の切り替えで転勤や入学など生活環境が変わる人は、新しい地域の防災情報をチェックすることが大切です。災害時の家族連絡手段(電話・SNS・緊急伝言ダイヤルなど)をあらかじめ確認しておくのも有効な備えとなるでしょう。
6-2. 台風・豪雨シーズンと水害対策
近年、台風や集中豪雨が引き起こす水害・土砂災害の被害が深刻化しています。2025年度においても、梅雨時期(6〜7月)や台風シーズン(7〜10月)に大雨のリスクが高まります。記録的な線状降水帯による河川氾濫や土砂崩れなど、災害に対する備えは不可欠です。
- 水害ハザードマップ:自治体発行のハザードマップを確認し、自宅や通勤通学路が危険区域に該当するか確認。
- 排水設備の点検:ゲリラ豪雨時にマンホールや排水口が逆流しないよう、住宅やオフィス周辺の排水設備を整備・点検する。
- 早めの避難:大雨や台風接近が予想される場合、行政の避難勧告を待たず、低地・河川近くの住人は早期に高台や避難所への移動を検討。
また、台風の進路情報や雨量予測は気象庁や民間気象会社の公式アプリやウェブサイトで随時アップデートされます。台風通過前に買い出しや備蓄を済ませるなど、十分な事前準備が被害軽減につながります。
6-3. 冬季の雪害・寒波への対応
日本海側や北日本では、冬季(12〜2月)に大雪や吹雪がしばしば発生します。豪雪地帯では除雪に追われたり、道路の凍結や立ち往生事故が起きやすく、命にかかわることもあります。過去にも大寒波による交通障害や孤立集落が報道され、対応が問題視されたことがあります。
- スタッドレスタイヤ・チェーン:降雪地域へ車で移動する際は必須。早めのタイヤ交換で急な積雪に対応できるようにする。
- 暖房器具と換気:室内で石油ストーブやガスヒーターを使用するときは、一酸化炭素中毒を防ぐため定期的に換気を行う。
- 避難ルートの確保:大雪でドアが開かなくなったり、外階段が埋まったりするケースがあるため、物理的なルートの確保が重要。
特に新年度の転勤や進学で雪国に引っ越す場合、未経験者にとっては降雪時の運転や寒冷対策の知識が不足しがちです。地域の人々に積雪時の交通ルールや除雪のノウハウを教わるなど、事前に十分な情報収集を行うことが求められます。
6-4. 火山・その他リスクと情報収集
日本には数多くの活火山があります。桜島(鹿児島県)や浅間山(群馬県・長野県)、富士山(山梨県・静岡県)など、噴火警戒レベルの変動があり得る山々では、防災情報のこまめなチェックが必要です。もしも旅行や登山を計画する場合は気象庁の「噴火警戒レベル」や自治体の通行規制情報を確認しましょう。
- 気象庁火山情報:噴火警戒レベルが1〜5段階で示され、レベルが上がると立ち入り禁止範囲が拡大する。
- 火山灰対策:噴火が予想される場合はゴーグルやマスク、帽子を用意し、車のエアフィルターの詰まりなどにも注意が必要。
その他、異常気象や落雷、突風、黄砂、PM2.5など、自然現象による被害リスクも多様化しています。防災アプリを活用すれば、気象警報・注意報や避難情報をリアルタイムで受け取れるため、忙しい時期でも状況を把握しやすくなります。特に年度初めのバタバタした時期ほど、いざというときの連絡体制を再点検することが肝要です。
6-5. 地域コミュニティと防災意識
大規模災害が発生した場合、公助(行政機関の支援)だけでなく、自助(個人の備え)や共助(地域コミュニティの協力)が不可欠です。年度の切り替えで引っ越しが増える時期には、新住民が地域の防災訓練や自治会活動に参加しにくい一面もあります。あらかじめ自治体広報や回覧板などで情報を得て、顔を合わせる機会を大切にすると、非常時に助け合える関係づくりがしやすくなります。
- 自治体主催の防災イベント:年に数回行われる防災フェアや防災訓練に参加し、地域の災害拠点や備蓄倉庫の場所を把握する。
- 近隣住民との情報交換:SNSの町内グループやLINEなどで連絡網を整備し、災害発生時に安否確認や物資の融通をスムーズに行えるようにする。
- 自主防災組織:消防団や自主防災会など、地元コミュニティによる防災ネットワークが充実している地域もあります。関心のある方は積極的に参加を検討してください。
2025年度は、大阪・関西万博や世界陸上など多くの人が集まる行事が予定されています。大規模イベント時にはテロ対策や雑踏事故防止なども課題となるため、運営側と来場者の双方に防災意識が求められるでしょう。