だがしの日 (記念日 3月12日)
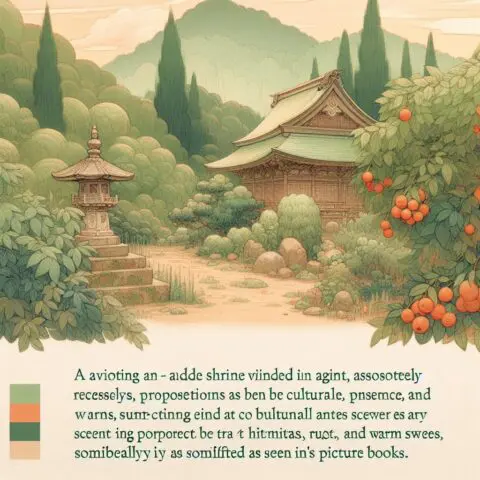
知っていますか?「だがしの日」は、ただのお菓子の記念日ではありません。岡山県瀬戸内市に事務局を置き、全国の駄菓子メーカーが結集して制定されたこの日は、日本のお菓子文化、そしてその背後にある深い歴史と伝統を祝う特別な意味を持っています。
だがしの日の起源と意義
制定の背景
「DAGASHIで世界を笑顔にする会」によって2015年に制定された「だがしの日」は、日本の駄菓子業界を活性化させるとともに、DAGASHIを通じて世界平和のメッセージを発信することを目指しています。
この記念日は、お菓子の神様・菓祖として知られる田道間守公を祀る和歌山県海南市の橘本神社の前山和範宮司の提唱により、田道間守公の命日である3月12日に設定されました。
「駄菓子の日」ではなく「だがしの日」としたのは、子どもたちにも親しみやすい名前として、また大人たちへの配慮からです。
この日には、さまざまなイベントが開催され、子どもたちがゲームを楽しみながら駄菓子をもらえる機会が提供されます。
田道間守公とは
田道間守公は、『日本書紀』や『古事記』に記される伝説の人物で、新羅の王子・天日槍の5世の子孫とされています。垂仁天皇の命により、常世の国から非時香菓(タチバナの実)を持ち帰ったとされ、その功績から菓子神・菓祖として崇敬されています。
橘本神社の元の鎮座地「六本樹の丘」は、田道間守が持ち帰った橘が初めて移植された地と伝えられており、これが後にミカンになったという伝承があります。
中嶋神社や橘本神社では、田道間守公を祀り、菓子祭やみかん祭などの例祭が行われています。これらの祭りでは、全国の菓子屋から供えられる菓子や、業界の繁栄を祈願する製菓業者の参列が見られます。
このように、「だがしの日」は、日本古来のお菓子に対する敬意と感謝の気持ちを表す日であり、その背景には豊かな歴史と文化が息づいています。
日本の駄菓子文化とその魅力
駄菓子の特徴と楽しみ方
駄菓子とは、手軽に楽しめる低価格のお菓子のことを指し、その種類は豊富です。子どもたちにとっては、小銭で買える楽しみの宝庫であり、大人にとっては懐かしさを感じさせるアイテムです。
駄菓子屋では、お菓子だけでなく、おもちゃやゲームなども楽しめるため、子どもたちのコミュニケーションの場ともなっています。
また、駄菓子は、日本の四季や行事にちなんだものも多く、季節感を感じさせる楽しみもあります。
「だがしの日」には、家族や友人と一緒に駄菓子屋を訪れ、様々な駄菓子を味わいながら、日本のお菓子文化を存分に楽しむことができます。
駄菓子と日本の文化
駄菓子は、日本の精神や文化が凝縮されたものと言えます。例えば、お正月に食べる縁起物のお菓子や、夏祭りで楽しむ焼き菓子など、駄菓子には日本の伝統や風習が反映されています。
また、駄菓子屋は地域社会のコミュニケーションの場としての役割も担っており、日本の地域文化の一端を支えています。
「だがしの日」を通じて、駄菓子文化の魅力や重要性を再認識することは、現代の忙しい生活の中で、大切な文化遺産を守り、次世代に伝えていくためにも重要です。
この記念日は、日本のお菓子文化を世界に広める機会ともなり、国際的な交流の促進にも寄与しています。
だがしの日を楽しむためのアイデア
イベントの参加と体験
「だがしの日」には、全国各地で様々なイベントが開催されます。家族や友人と一緒に参加し、駄菓子を楽しみながら、日本のお菓子文化を深く知ることができる絶好の機会です。
また、この記念日を機に、自宅で駄菓子パーティーを開催するのもおすすめです。様々な駄菓子を用意し、昔話や駄菓子にまつわるエピソードを共有しながら、楽しい時間を過ごすことができます。
さらに、駄菓子屋巡りをして、地域によって異なる駄菓子の種類や特徴を発見するのも面白いでしょう。地元の駄菓子屋さんを支援する意味でも、このような活動は価値があります。
「だがしの日」は、単にお菓子を楽しむ日ではなく、日本の豊かな文化と歴史を感じることができる特別な日です。この記念日を通じて、日本のお菓子文化の素晴らしさを再発見し、世界にその魅力を広めていくことができれば幸いです。
